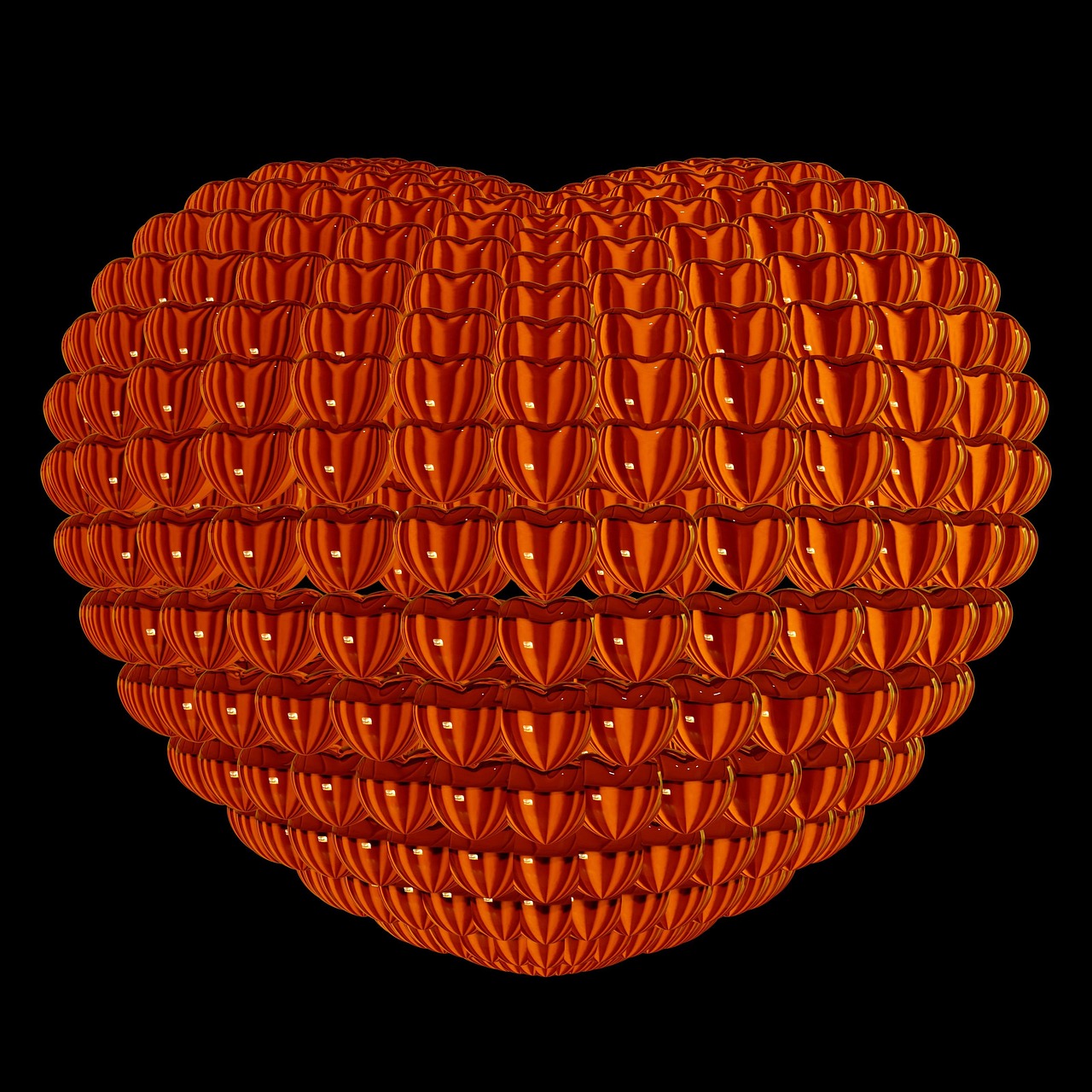【第4回】アンバー職場の未来:型を守るだけでは限界、“接客する知性”への進化できるか
1. はじめに
「うちは昔からこのやり方でやってきたから」
そんな言葉が安心感として機能していた時代が、確かにありました。
日本社会に深く根づく“アンバー職場”——それは、上司に従い、ルールに忠実に、周囲と同じ空気を読むことで秩序を保つ文化。
特に大企業や行政、金融、教育などの現場では、いまも根強く残っています。
けれども、AIの導入や業務の自動化が急速に進む今、
これまで「守るべき型」とされてきたものが、じわじわと無効化されつつあるのではないか?
そう感じさせる出来事が、あちこちで起きています。
2. アンバー職場の特徴と功罪
アンバー文化の根幹には「型」があります。
「上司の言うことを聞く」「会議では立場の順に発言する」「マニュアルを守る」「報告・連絡・相談を欠かさない」——
こうした形式が“正解”として共有されており、従うことで安心できる仕組みになっています。
確かに、教育コストは低く、失敗も起きにくい。
組織としてはとても安定しやすい反面、変化に弱く、属人性に頼った運用も温存されがちです。
加えて、“なぜそれをやるのか”を考える習慣が育ちにくいため、新しい風を取り入れることが苦手な傾向もあります。
3. 日本郵便の事例に見る “アンバーからオレンジ”への失敗
かつて日本郵便が民営化された際、一部の現場では営業ノルマが導入され、
「自爆営業」や「精神的ストレス」による過労が問題視されました。
それまで、地域に根ざしたサービスを丁寧にこなしてきた職員たちは、
アンバー的な価値観——「忠実に任務をこなす」「上司に従う」「空気を読む」——の中で職務をまっとうしていた人たちです。
そこに突然、「成果を数字で出せ」「売り上げを上げろ」という“オレンジ的”な指標が持ち込まれたとき、
彼らがよりどころにしてきた「型」が崩壊してしまったのではないでしょうか。
型を壊す前に、新しい型は提示されていただろうか?
成果を求めるのであれば、そのやり方・考え方・目的を共有する時間があっただろうか?
これは日本郵便だけの話ではなく、
多くのアンバー職場が「型を守りながら、突然成果を求められる」という矛盾に直面しているのではないでしょうか。

4. 上司と部下の分断:「求め方だけがオレンジ化」した現場
この問題は、実は“文化”というより“関係性”の問題かもしれません。
アンバー文化では、「上司が型を与え、部下はその通りに動く」という関係が前提でした。
ところが、成果主義が持ち込まれると、上司が「数字を出せ」とだけ言い、
部下は「そのやり方が分からない」まま放置されるという現象が起こります。
上司は「自分も上から成果を求められている」と焦り、
部下にそのままプレッシャーを下ろす。
しかし、その成果をどう出すか、何を変えればいいかは具体的に提示されない。
結果として、部下は「型がないのに責められる」という状態に追い込まれます。
この“求める側”と“支援が必要な側”のズレこそが、アンバー職場のひずみを生んだ最大の要因ではないでしょうか。
5. AIはアンバー文化を飲み込むのか?
もう一つ、構造的に大きな変化があります。それがAIの登場です。
アンバー職場の特徴である「ルール」「承認フロー」「定型業務」こそ、
AIやRPAが最も得意とする分野です。
つまり、「型に忠実に従うこと」自体が、機械に置き換えられるフェーズに入っています。
さらに言えば、上司が行ってきた“判断”や“指示”すら、AIによって代替され始めているのです。
「言われた通りにやる部下」も、「型を与えるだけの上司」も、
このままではAIに“飲み込まれる側”に回ってしまうかもしれません。
6. 生き残る道:グリーン化か、“意味ある”オレンジ化か
では、アンバー職場はどうすれば生き残れるのでしょうか。
一つの道は、グリーンへの進化です。
つまり、共感・対話・傾聴をベースにした職場文化を育てること。
ただし、ここで大事なのは、部下がグリーン化するには、上司もまたグリーンである必要があるということです。
「上司は従来型のまま、部下だけ変われ」では、関係性の変化は起きません。
もう一つの道は、オレンジへの再構築。
ただしそれは、「成果だけを求める」のではなく、
「成果の意味を共に定義し、目的とプロセスを共有する」形でなければ、また失敗を繰り返すことになります。
部下だけが変わればよいのでしょうか? いいえ、上司も含めて一緒に進化する必要があります。
こうした進化を実現するために必要なのが、本来の意味でのリスキリングです。
リスキリングという言葉はよく使われますが、それは単に新しい技術を学ぶことではありません。
本質的には、職場の「型」が変わるときに、自分自身の役割や視点も変えていくこと——
つまり、「関係性の再構築」や「問い直す力」こそが、AI時代のリスキリングの核心ではないでしょうか。
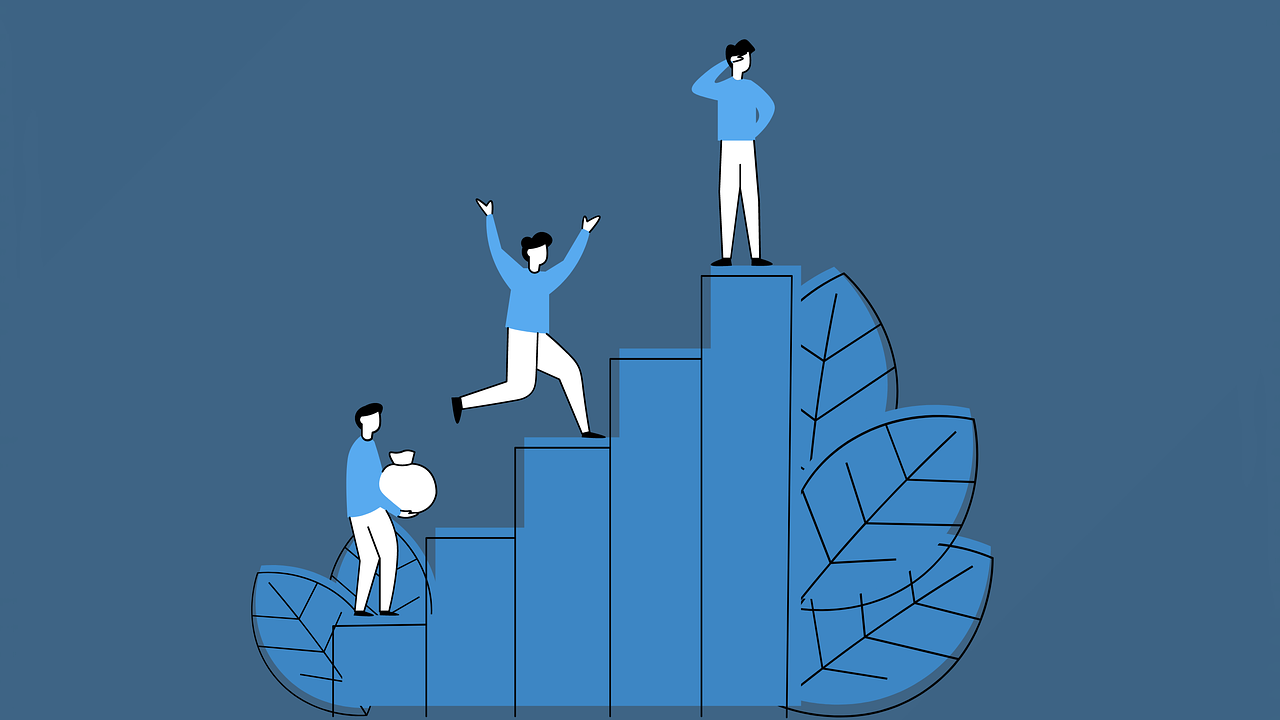
7. 管理職の再定義と、現場の“コンシェルジュ化”
ある鉄道会社の役員は、こう語っていたそうです。
「将来、AIや自動化が進めば、社員はもっとお客様の前に出て、旅を楽しんでいただく存在になるべきだ」
これは、未来のアンバー職場の在り方を象徴する考え方だと思います。
AIが型を代替するなら、人は意味を担うべきなのです。
つまり、接客・対話・文脈理解といった“人間にしかできない領域”が求められます。
管理職もまた、「ルールを守らせる人」ではなく、
「なぜそれが必要なのかを共に考える存在」へと進化していく必要があるのではないでしょうか。
これもまた、関係性を変えるためのリスキリングです。
8. 結論:問いに向き合える職場だけが生き残る
アンバー文化がすべて悪いわけではありません。
基礎となる型があることは、人に安心感と自信を与え、応用や挑戦の土台を築いてきました。
けれどもAI時代に求められるのは、「なぜその型を守るのか」を自ら問い直せる力です。
そして、上司と部下が“従う・指示する”関係を超えて、
“意味を共に育てる”関係に変わっていけるかどうか。
リスキリングとは、本来、組織や職場の「型」が変わるときに必要となる、内面的な再構築なのかもしれません。
上司と部下の関係が変わり、AIが型を代替する時代に、私たちは“人としての価値”をどう更新していくか。
そこにこそ、真のリスキリングの意味があるのではないでしょうか。
アンバー職場がこれからも価値を持ち続けるためには、
まさにいま、この問いに正面から向き合う必要があるのです。
次回は、「成果」や「成長」を軸に動く“オレンジ職場”を掘り下げていきます。AI時代における競争と共創、そしてヒトの役割はどのように変わるのか?お楽しみに。