第4話 オレンジ職場で共有が進まない理由 ─情報を出すと損すると思っていませんか?
■ はじめに:ツールがあるけど、なぜか情報共有されない?
前回(第3話)では、「あとでまとめる」文化が生む二度手間・三度手間と、TeamsとOneNoteなどの組み合わせによる“同時に書く”働き方を紹介しました。
紙にメモ → 清書 → 共有
ファイルを回収 → 取りまとめ → 再送
このような紙やファイルに基づいたアプローチは、ツールとルール(業務プロセス)を整えなおすことで大きくその手間を減らせます。
では、クラウドに保存され、共同編集もできるようになった職場では、もう安心なのでしょうか?
──実は、そこから先に“もうひとつの壁”があるのです。
便利な共有ツールはあっても、
- 誰もチーム投稿を書かない
- 会議メモは、結局誰かがこっそりまとめている
- ファイルは、また個人フォルダにしまいこまれていく
この現象、見覚えありませんか?
これはもう、ツールや操作の問題ではなく、「職場文化」そのものの問題です。
※ 職場文化の色分けについては、こちらの記事で全体像を解説しています
→ 「職場の色分けとは?」
■ オレンジ職場とは:「成果=個人評価」の文化
こうした職場の多くは、「オレンジ職場」と呼ばれる文化を色濃く残しています。
- 成果は個人に紐づき、評価も個人ベース
- ノウハウや情報は“自分の武器”として囲い込む
- うかつに出すと“手柄を奪われる”ように感じてしまう
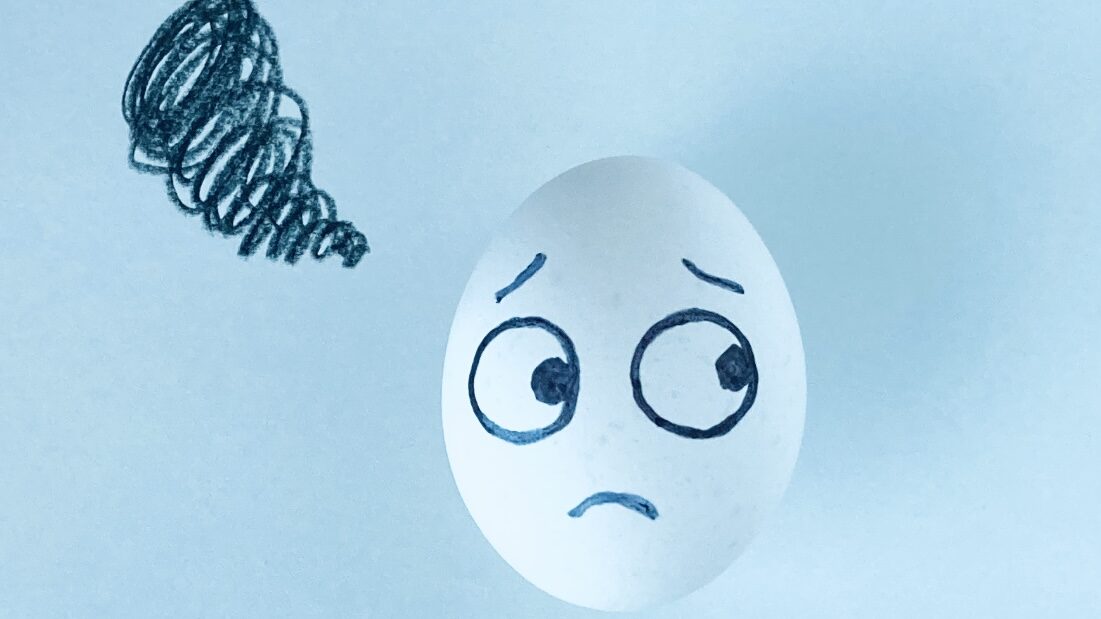
この空気の中では、情報を出すことそのものが“損”に思えてしまうのです。
ツールがどれだけ進化しても、この職場の文化が変わらなければ、共有は進みません。
■ 今、社会全体が求めているのは“グリーンな職場”
一方で、今の社会や経営層が目指している職場像は、こんな価値観ではないでしょうか?
- 一人の成果より、チームでの貢献と協働
- 共感と対話を重視する心理的安全性
- 情報の透明性が、仕事の速さと質に直結する
これは、「グリーン職場」と呼ばれる文化に近いものです。

つまり、情報を共有しないことが、今の時代ではむしろ“足かせ”になる──
そんな逆転が起きているのです。
■ オレンジの職場文化がTeamsを止めてしまう
TeamsやLoopといったツールは、グリーンな働き方にこそフィットします。
しかし、オレンジ文化の職場では、こうなりがちです:
- チーム投稿は「偉い人だけが書く場」になる
- やりとりは裏チャットや口頭で済ませ、「見える化」を避ける
- 成果報告はギリギリまで伏せて、最後に“ドン”と出す
こうして、共有の場が「見せたくない空気」で静かになってしまうのです。
■ ツール × プロセス × 文化の視点から考える
ここで視点を整理してみましょう。
- ツールは、すでに十分に揃っています
- 問題は、それをどう使うかというプロセス(運用の仕方)
- そしてそれを支える、職場の文化(空気・評価・安心感)
この3つが揃って初めて、情報共有は自然に機能します。
これが、SawaLeaf が提唱する「ツール × プロセス × 文化」の三位一体の変革アプローチです。
そしてこのうち職場の「文化」変革こそが、最も時間がかかるし、最も根深い。
だから現場ではこう思われがちです:
「それって会社が決めることでしょ」
「うちの制度では評価されないからムリだよ」
でも、ちょっとだけ見方を変えてみてください。
“職場単位”なら、できることはあるんです。
■ 共有する人が“損しない”職場をつくろう
職場文化はすぐには変えられません。
でも、「情報を出した人が損をしない」設計なら、すぐに始められます。
たとえば:
- 投稿に対して👍や🙌などのリアクションを返す習慣をつくる
- 上司が「ありがとう」「助かった」とその場で言葉にする
- 会議で「その話、ぜひ投稿してもらえる?」と促すルールをつくる
- 投稿されたノウハウを「この件なら◯◯さん」と専門家として自然に参照する
- 毎週「チーム内ベスト投稿」を選んで感謝や注目を集める仕掛けをつくる
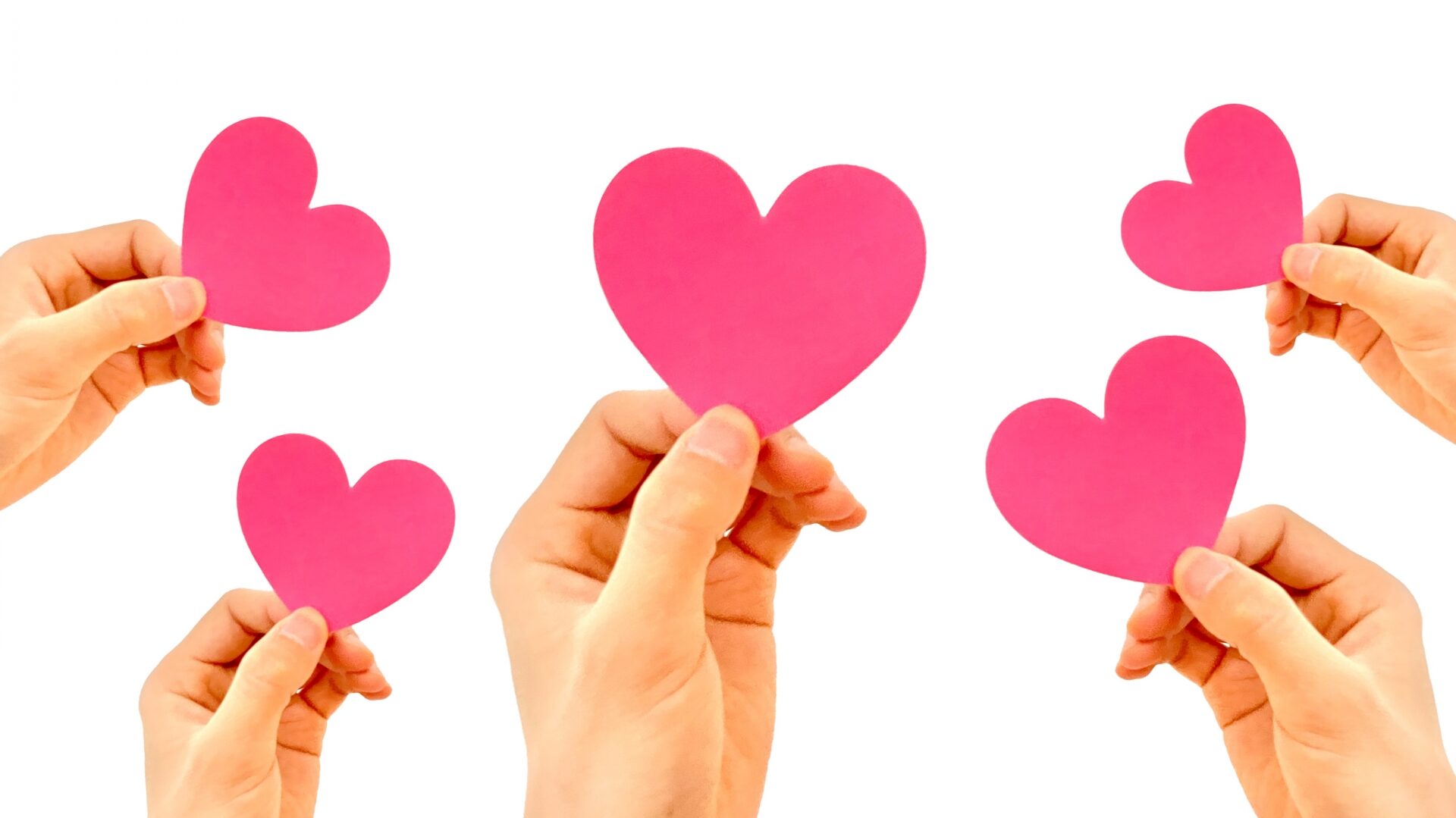
こうした積み重ねで、「情報を出す人の方がかっこいい」という空気が育ちます。
■ 上司・リーダーの関わりが文化を動かす
特に大きな影響を与えるのが、上司・リーダーの関わり方です。
- チーム投稿に反応して、「ありがとう」と声をかける
- 「こういう投稿をもっと見たい」と前向きに期待を伝える
- 会議や日報などで、チーム投稿を評価の材料として取り上げる
こうした行動が、「情報を出しても大丈夫」「むしろ出した方が良い」という安心感と正当な評価につながります。
■ まとめ:職場文化はツールでは変わらない。でも、ツールをきっかけに変えられる
Teamsを中心とする多くのM365のツールは、情報共有を加速するために設計された優れたツールです。
でも、それが機能するかどうかは、職場の文化にかかっているのです。
- 情報を持っている人が偉いとか、
- 出し惜しみした方が評価される、
- 一人で頑張る姿の方が印象に残るなど、
──そんな考え方を、少しずつ手放していきましょう。
「チームで成果を出すには、情報を出して連携する人が必要なんだ」
そんな感覚が芽生えるだけで、職場の空気は動き出します。
次回予告:情報共有のその先へ──Loopという新しい共有スタイル
次回は、情報共有の“その先”についてお話しします。
投稿でもチャットでもない、「第三の共有スタイル」として注目されるLoopとは何か。
今、Microsoftが提示する「共有の未来」を、一緒に覗いてみましょう。
🗳️ あなたの職場ではどうですか?
次の話を読む
→ 第5話 心理的安全性がチームを強くする ─ Microsoft Loopと次世代の職場文化
🧭仕事の「やり方」を変える前に、一度「状況」を整理しませんか? ツールを整えても拭えない違和感があるなら、それは職場文化の土壌を整えるタイミングかもしれません。今の歩みを重くしている「正体」を言葉にし、次の一歩を導き出す対話セッション Compass をご案内しています。
