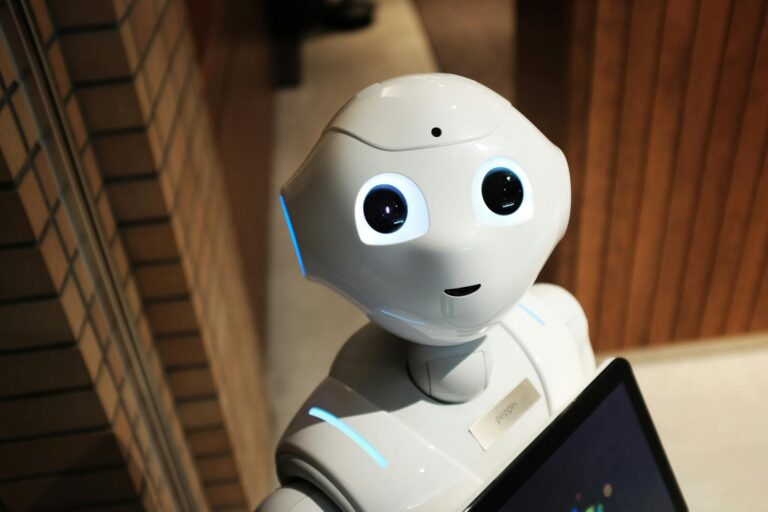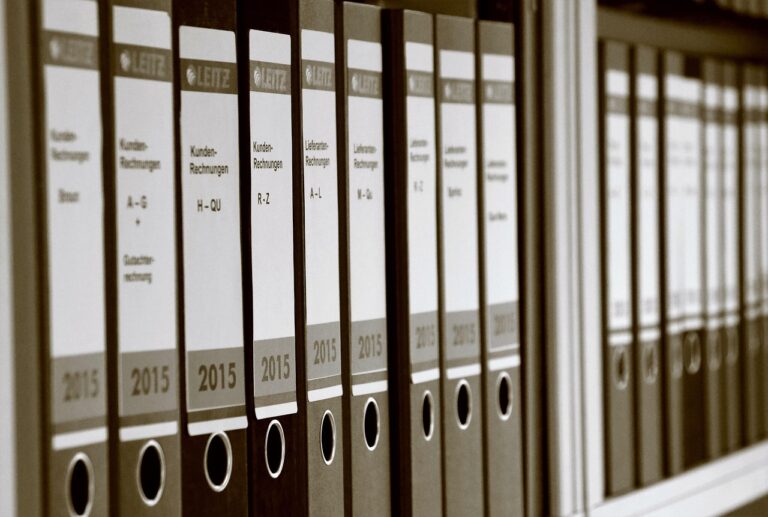【第7回】ティール職場の未来:自律を支えるAIと循環するリーダーシップ
1. はじめに
ティール型の職場と聞くと、「理想の働き方」や「最終進化系」のような印象を持たれることがあります。しかし私たちはこの色分けを、個人の成長段階ではなく、職場ごとの文化の構成を把握するための視点と捉えています。
人は人生の中で、いくつもの職場や組織を経験します。ある時期にはティール的な文化の中で働き、またある時期にはレッドやオレンジの職場で重要な役割を担うこともあるでしょう。つまり、「ティール=上位」ではなく、目的や状況に応じて、必要な職場文化が異なるのです。
今回はその中でも「ティール職場」の骨組みについて掘り下げます。
AI時代におけるティール型の特徴や、その強みと課題を整理し、どのような構造がその職場文化を支えているのかを見ていきます。
2. ティール職場とは「自律と目的に支えられた関係」
ティール的な職場の代表例として、ひとつ救命救急の現場が挙げられます。そこでは、「命を守る」という共通の目的に向かって、誰もが自分の任務を理解し、即座に行動に移していきます。
このとき大切なのは、「言われて動く」わけでも、「任されて動く」わけでもないということです。一人ひとりが自ら考え、自ら行動し、必要であれば学び直し、状況に応じて進化する。それがティール職場における“自律”です。

目的への共感を起点に、誰かに依存せず、誰かを指示せず、自然に行動が起きていく構造こそ、ティールの基盤となる関係性です。
3. リーダーは「固定」ではなく「循環」し、必要に応じて相互補完する
ティール職場では、上司と部下という構造は希薄です。だからといって、誰もリードしないわけではありません。その場に応じて最適な人が自然と前に出る、そんな信頼に基づいた関係が成り立っています。

例えば、ある営業の場面では営業担当者が主導し、導入フェーズでは技術担当者が前に立つように、役割や専門性に応じて“リード”が柔軟に入れ替わるのが特徴です。医療現場で言えば、形成外科・外科・麻酔科といった複数の専門医が、ケースに応じて連携し合いながら、必要な人が必要なタイミングで“自然に前に出る”という構造に近いかもしれません。
こうした“相互補完的な循環リーダーシップ”が機能するためには、チーム全体がその構造を理解し、共有していることが不可欠です。誰がいつ前に出ても不自然にならないように、全員が「どう動くのがこのチームにとって自然か」を感覚的に掴んでいる状態が求められます。
その共通理解があるからこそ、誰かが前に出ても引っ張り下ろされることなく、逆に後方支援にも自然に回れるのです。
リーダーシップは「肩書き」で与えられるものではなく、状況と目的に応じて“流動的に現れる”ものとして機能します。ティールの骨組みは、「誰が上か」ではなく、「今、この目的に最も適した人は誰か」という問いで支えられています。
4. AIとティール職場:仲間としての「自己進化サポーター」
ティール職場において、AIは単なる道具ではなく、“進化を支える存在”になり得ます。

たとえば、自分の弱点に気づいたとき、AIが学びの資料を提示してくれたり、チーム内の知見を引き出してくれたりすることで、個々人が自律的に成長する土壌を補完します。
また、ルーティン業務や調整業務はAIに任せることで、人はより創造性と判断力が求められる領域に集中できます。AIは“仲間の一人”として、静かにチームの進化を支えます。
ティール職場におけるAIの理想像は、「業務を代行する存在」ではなく、自分自身を補完してくれる“アドバイザー”です。
5. ティールの「骨組み」── 構造として見えてくる共通点
ティール職場には明確なマニュアルは存在しないかもしれませんが、そこには次のような「骨組み」ともいえる共通構造が存在しています。
- 共通目的の明示
誰もが「なぜこの仕事をしているのか」を理解し、そこに納得している - 自律の土壌
形式的な役割分担より、互いの信頼と尊重に基づいて自然と動く構造がある - リーダーの循環構造と相互補完
状況ごとに主導権が柔軟に移り、専門性が連携し合う関係が築かれている
※そして、その構造がチーム全員に共有されている - 自己進化の支援構造
自分で自分を育てようとする意欲に対して、周囲とAIが支え合う
こうした構造があって初めて、「自律的で信頼に満ちた職場」が成立します。
6. 色は固定されず、職場内にも混在する
ティール職場が理想に見えることもありますが、すべての職場がティール型である必要はありません。たとえば、新入社員の研修では、明確なルールと手順が求められるため、アンバー的な文化が適しています。
同じ職場内でも、研修はアンバー、日々の業務はグリーンやティール、といった“色の混在”は自然な現象です。
このモデルはあくまで、「職場の文化構成を見える化し、強みと課題を把握するためのもの」です。
その意味で、「いま自分たちの職場はどの色がどの程度混在しているか」を知ることが、最初の一歩になります。
7. おわりに:意思ある職場がAI時代に強くなる
AIが進化すればするほど、AIでは補えないものが浮き彫りになります。
それがヒトの「意志」や「信頼」でつながる職場文化です。
ティール職場は、その代表的なあり方の一つです。
ただし、すべての職場がティール型を目指す必要はありません。
ティールは、ある目的を持った人たちが集まり、自然に構成された職場文化のひとつであるだけで、状況や目的によって、アンバーやオレンジの構造が適している場合もあります。

これからAIを活用する上で重要なことは、単に業務を効率化を目指すことではなく、
自分たちの職場がどのような構造を持ち、どのような職場文化を、どの方向に加速させたいのかを正しく判断してAIを活用することだと言えるでしょう。
そして、どのような職場環境だったとしても、そこに働くヒトの“意思”がある職場は、これからますます強くなっていくはずです。
次回は、職場の特色に合わせて、AIをどう活用するかをまとめてみます。どうぞお楽しみに