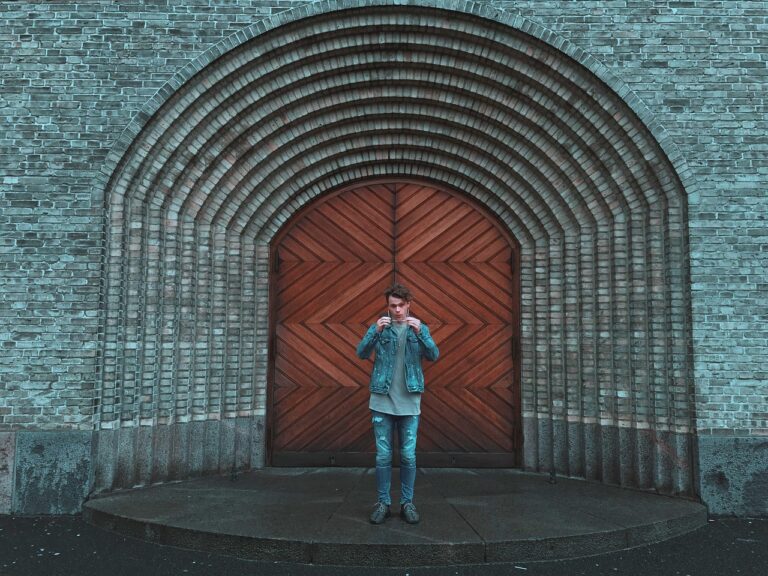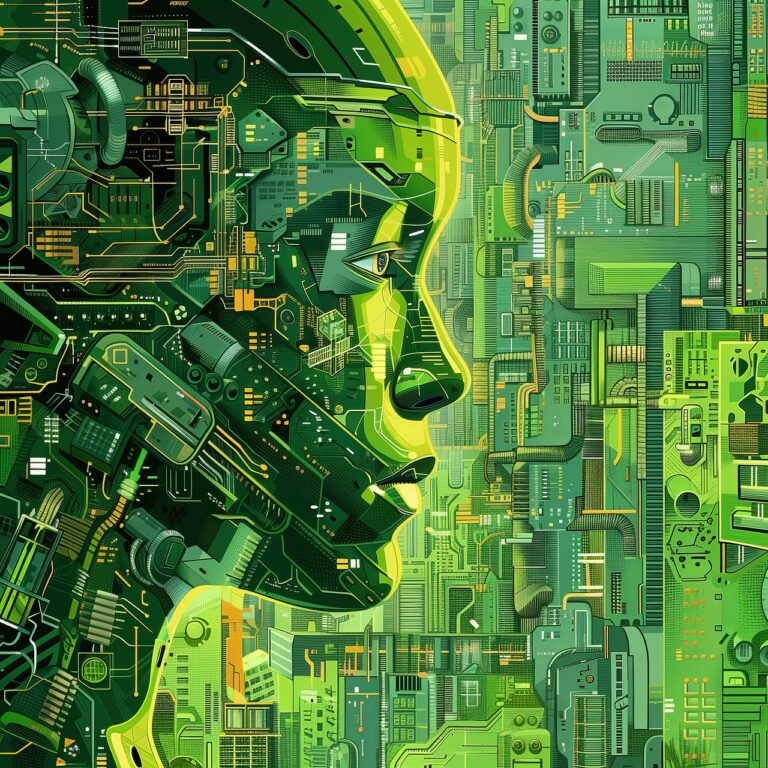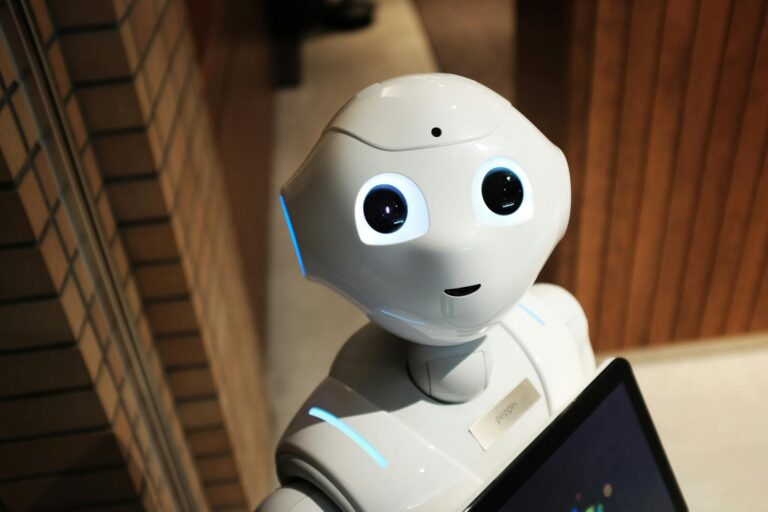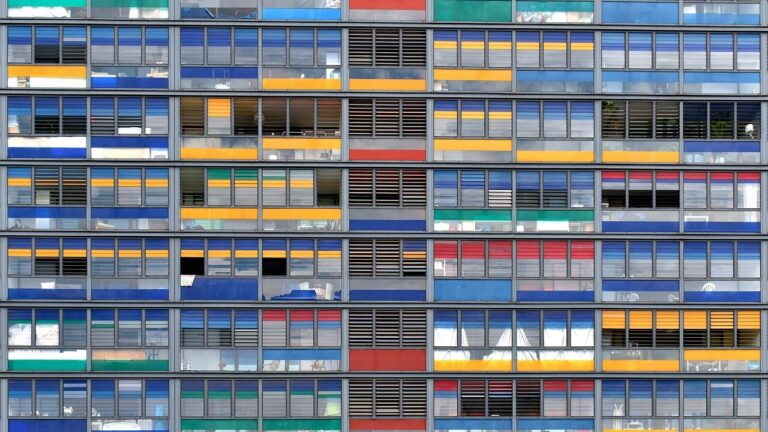【第5回】オレンジ職場の未来:AIと共創する成果主義の次なる姿
1. はじめに
成果主義と言えば、今のビジネスパーソンにとってはとても馴染み深い言葉かもしれません。数字で語り、目標を追い、結果を出す——そんな「オレンジ職場」の文化は、多くの企業の推進力となってきました。でも、そこには一方で見えにくい「課題」も隠れています。そして、AI時代を迎えたいま、オレンジ職場の価値観そのものが大きく揺れ始めています。
2. オレンジ職場の強みと、これからの進化
オレンジ職場の最大の特徴は、成果にこだわる「推進力」です。KPIやOKRといった目標を掲げ、それを達成することに全力を注ぐ。その文化は、短期的な成長や目に見える業績を支える大きな柱になっています。
しかしAIが急速に進化する中で、ただ数をこなすだけの成果主義では十分とは言えなくなっています。AIによるデータ解析のスピードや正確さは、人間の能力をはるかに超えています。これからは「量」ではなく「質」、そして「新しい価値」を問われる時代に入ってきています。
3. AIと共創する新しい個人像
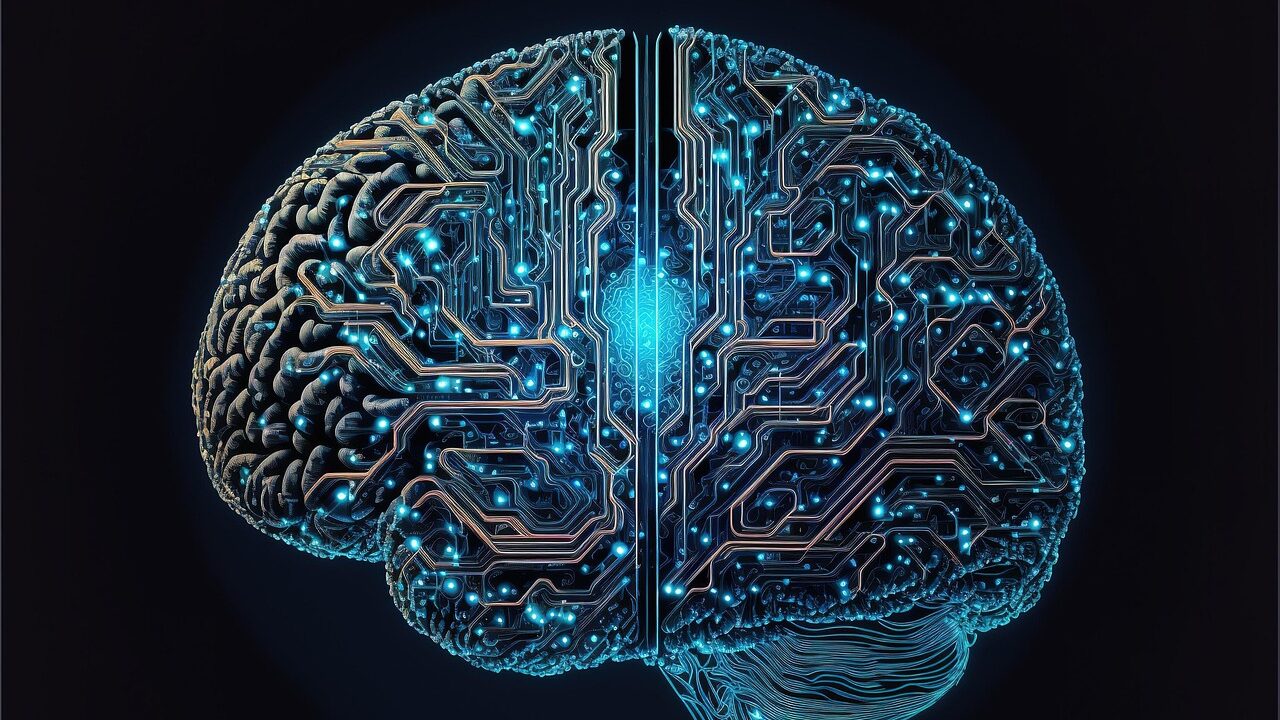
オレンジ職場における「個人の力」は、これからAIと組むことでさらに拡張されます。部下の視点では、AIがまるで「拡張された脳」のように機能し、タスク整理や優先順位付け、情報収集をサポートしてくれる存在です。これにより、経験や勘に頼るだけでなく、より戦略的に成果を創出できるようになります。
補足:
実業家の堀江貴文さんは、AIを「人間の脳機能の拡張」と表現しています。車が人の脚を助け、道具が手の役割を広げてきたように、AIは「思考・判断の拡張脳」として機能し、「記憶」「思考」「判断」などにおける高度な補完を担う存在であると語っています。
一方、上司の視点では、部下のAI活用状況を理解し、伴走しながら成長を後押しする役割が求められます。従来の「指示する上司」から、「共に学び、共に成果を育てるリーダー」へと進化する必要があります。
これまで多くの組織では、成果主義を取り入れる一方で、現場の上司がルールや秩序を重視する「アンバー的管理者」のままであることが少なくありませんでした。その結果、成果を追う圧力が強まりすぎることで、精神的な疲弊やチームの分断を引き起こすリスクが顕在化しています。
このことは、ノルマを課すだけの管理型リーダーシップでは、組織の成果も人の成長も守れないことを痛感させます。AI時代において上司に求められるのは、部下がAIと協働して成果を生むプロセスを理解し、そのプロセスも含めて評価し伴走する能力です。
4. 成果主義の裏に潜む課題
オレンジ職場の成果主義は、一見すると合理的で強い仕組みですが、その裏にはいくつかの大きな落とし穴があります。
短期的な成果に偏りすぎると、会社としての中長期的なビジョンや共通目標が形骸化してしまいます。各自が目の前のKPIだけに集中し、チーム間の協力が減り、結果として組織全体の大きな成果が出しにくくなる。
また、個人主義が進むと「誰かを助ける」よりも「自分が勝つ」ことが優先され、組織の一体感や信頼関係が失われます。その結果、人材のバーンアウトや早期離職、ナレッジ共有の停滞といった副作用が表面化します。
ここで注目したいのが、グリーン職場との対比です。グリーン職場では、共感や対話を通じてチームの成長と全体最適を目指します。一方、オレンジ職場は個人の成果を最大化する方向に偏りやすいため、全体のゴールやチームの持続的な力を育む視点が弱くなりがちです。
5. AI時代に求められる新たなバランス

AIは、オレンジ職場の強みである「スピード」「量」を加速させる強力なツールです。しかし、それだけでは組織の持続的成長にはつながりません。むしろ、AIが成果を加速させるからこそ「どう使うか」を問い直す必要があります。
誰と、どのように成果を出すのか。AIを使うことでチームや組織にどんな影響が出るのか。これからは「個人の成果」だけでなく、その先にある「共創の価値」や「学び合う文化」が大切になります。
オレンジ職場の持つ推進力に、グリーン職場の共感や対話の要素をどう取り入れるか。このバランスこそが、AI時代に成果を持続可能にするカギになるでしょう。
6. まとめ
これからのオレンジ職場では、AIが「拡張された脳」となり、個人の力を飛躍的に高める可能性があります。しかし、その成果の使い方や共有の仕方を誤ると、組織全体が分断されてしまうリスクも孕んでいます。
成果主義の力を活かしつつ、共創や対話を通じた持続的な成長をどう実現するか——これが、これからのオレンジ職場に求められる問いです。
次回は「グリーン職場」に焦点を当て、共感と対話を軸にした進化のかたちを探っていきます。ぜひお楽しみに。