第5話 心理的安全性がチームを強くする ─ Microsoft Loopと次世代の職場文化
■ はじめに:「考えるところから共有する」時代がやってくる
これまでの4話で、Teamsを中心としたツールの進化、職場文化とのギャップ、共有の実践についてお話ししてきました。
そして今回は最終回として、Microsoft 365の中でも比較的新しく登場した
「Loop」(2023年11月 GA)というツールが示している、これからの職場の未来像について触れていきます。
まだ多くの人にとっては「名前は聞いたことある」「触ってみたけどうまく使えなかった」くらいかもしれません。
でも、このLoopの発想は、私たちの働き方がどこへ向かっているかを知る手がかりになります。
■ Loopの特徴は「考えを“ファイル化”せずに共有する」こと
従来のWordやExcel、PowerPointといったOfficeアプリは、
まず資料を作ってから、完成したものを共有するスタイルが基本でした。
でも、Loopは違います。
- ちょっとしたメモ
- 複数人で書きながら育てるチェックリスト
- 会議中に並行して書き出すアイデアの断片
こうした「思考のかけら」を、
ファイルにせずに、そのまま共有・編集できるのがLoopの強みです。
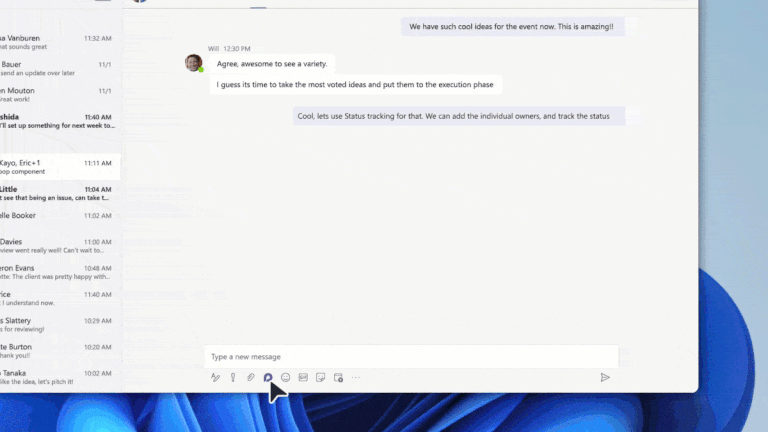
これまでの共有は「完成後」が前提でしたが、
Loopは「途中経過」「まだ考えている最中」から共有していけるのです。
■ Loopが活きるのは、グリーン職場のようなチーム構成
このような「思考の共創」が成立するには、前提条件があります。
- チームとしてゴールが共有されていること
- お互いの役割や責任の範囲が認識されていること
- 信頼関係があり、途中の考えを出すことに抵抗がないこと
こうした状態──つまりグリーン職場的な文化や構成が整っているほど、
Loopは自然に、そして強力に機能していきます。
※「グリーン職場って何?」と思った方は、こちらの記事をご覧ください:
👉グリーン職場の未来:強い部活と生成AIファシリテーター
■ マナーと合意がLoopの力を引き出す
ただし、Loopの良さを活かすには、チーム全体で「共有のマナー」を育てていくことが前提になります。 Loopでは、ファイル添付ではなく「そのままの思考」を誰でも編集できるため、ルールがないと上書きや混乱が起こりやすいのです。
これは、Teamsでの投稿スレッド運用にも通じるものがあります。 各自がスレッドにひとことずつ補足しながら育てていく「一緒に紙風船を共にたたき上げていく」ようなやりとりがあれば、読みやすく、参加しやすくなります。 一方で、誰かが一方的に質問だけを投げ込んだり、長いやり取りがスレッドに収まらず混線してしまうと、情報がかえって埋もれてしまうことも。
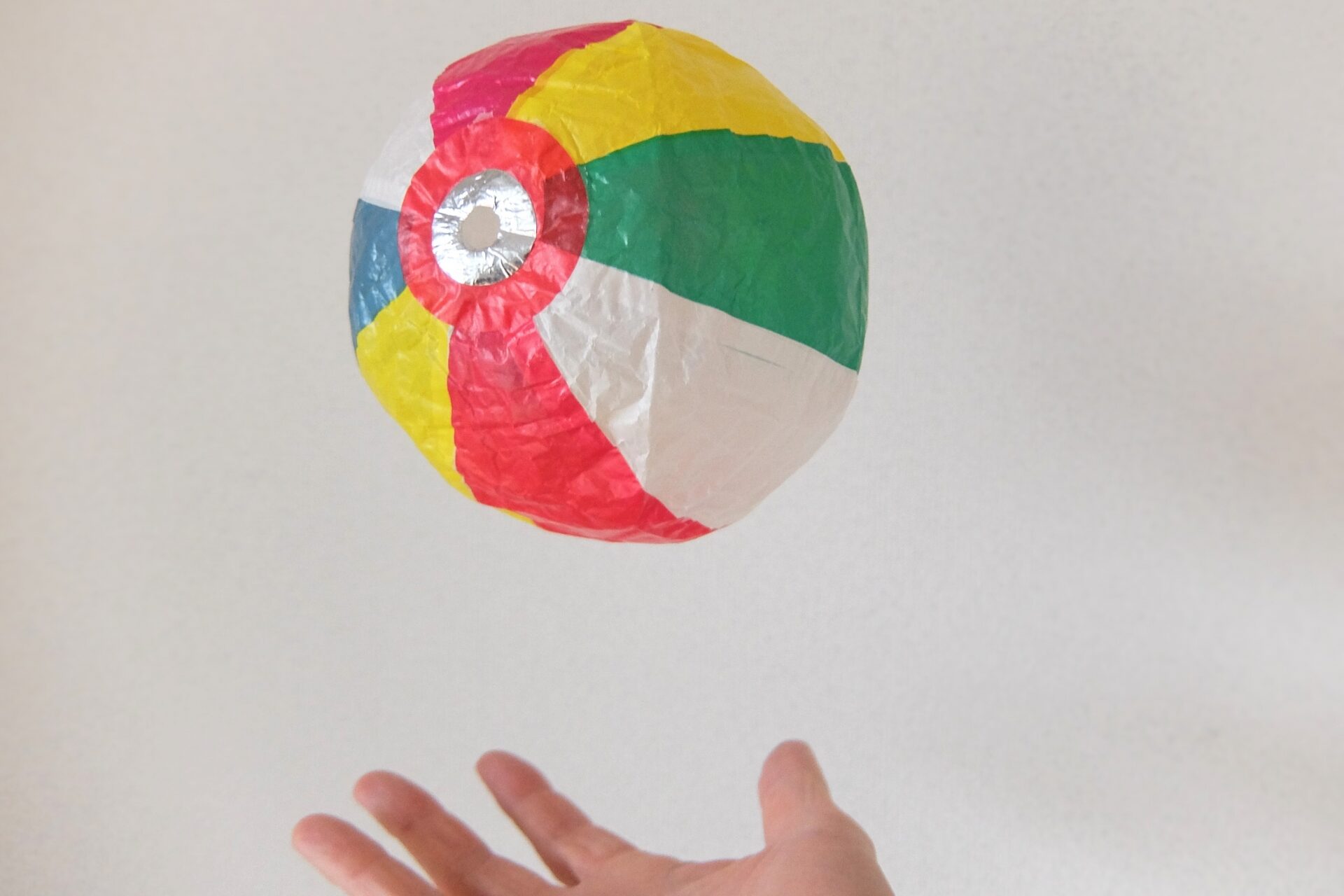
共有のやりとりは、“紙風船”のように、
軽やかに全員で育てていく感覚が大切
Loopも同様で、「自由に書いていいけど、チームでどう扱うかは共有しよう」という合意があってこそ、力を発揮します。 ただ使うのではなく、“どう使うかを話し合うところから始める”。それがLoopというツールの本質に合った使い方だと感じています。
■ グリーン職場の“次の一歩”とLoopの役割
多くの職場で、グリーン職場らしい「フラットな関係性」は芽生えつつあります。
けれども、「誰が情報を出す?どう判断する?どこまで関わっていい?」という線引きが曖昧なままでは、チーム内に“共有のためらい”が生まれがちです。
若手は「出しゃばっていいのか分からない」、ベテランは「余計な責任を背負いたくない」と感じ、誰も情報を出さず、LoopやCopilotのようなツールも活かされません。
ここで必要になるのが、心理的安全性と役割・連携の“フレームワーク”です。
安心して意見を出し合える空気と、自然に動きが回る仕組みがあれば、共有が加速し、Loopのようなツールもはじめて“職場の脳”として機能しはじめるのです。
この状態を、私はかつて別の記事で「強い部活」と表現しました。
この背景には、自然に先輩・後輩のリスペクトがあり、暗黙のフォーメーションがあるからこそ、考えを共有し、次へと渡していける。
Loopがもっとも輝くのは、そんな“心理的に安全で、動線が見えているチーム”なのかもしれません。

グリーン職場が進化すると、こんなチームが見えてくる。
■ LoopとCopilotがつくる「共創の場」
Loopが「人と人が考えを持ち寄る場」だとすれば、
Loop上のCopilotは「その場に加わり、アイデアを整理・提案する存在」です。
- Loop上で出てきた断片的なアイデアを、Copilotが整理して見やすくする
- 議論の流れをもとに、Copilotがたたき台を提案する
- チームのメンバーが加筆・修正して、AIと共に仕上げていく
これまでの「誰かが考え、みんなが確認する」というスタイルから、
「みんなで考え、AIも一緒に混ざって創る」スタイルへ。
LoopとCopilotは、その移行を現実のものにするための組み合わせなのです。
■ いま必要なくても、「どう使えるか」を知っておく価値がある
LoopやCopilotは、まだ本格的に活用されていない職場も多く、使いこなしにはチーム全体のデジタルリテラシーの向上や共通理解が不可欠です。 今すぐ導入しなくても、「どんな前提があれば使いこなせるか」を共に理解しておくことが、将来の選択を左右します。
- 自分たちは“思考の途中”を共有できるチームになっているか?
- そのための場所(Teams投稿・OneNote・Loopなど)はあるか?
- 役割とゴールが明確に共有されているか?
こうした問いに向き合っていくことで、単なるツール導入ではなく、文化的な準備が整っていくのです。 その準備こそが、未来の「共有スタイル」の質を大きく変えていきます。
■ まとめ:未来は「考えること」すら共有できるチームへ
LoopやCopilotが指し示しているのは、「考え方」や「判断の過程」すら共有していける未来です。 そこには、かつてのように「情報を持っている人が強い」という構造はありません。
未来にとって本当に価値があるのは、テクノロジーそのものではなく、
そのテクノロジーを活かす文化・信頼・共創関係が根づいたチームのあり方です。
シリーズを終えて:
「使っているのに、使いこなせていないのはなぜ?」の違和感に、光を当ててきたこのシリーズでは、Teamsというツールをきっかけに、私たちの「働き方そのもの」を見つめ直してきました。
LoopやCopilotは、その延長線上にある、次なる“未来の思考共有スタイル”です。
段階を踏んで育てていけるチームへ
そうした視点を持つことで、この時代がきっとあなたの味方になってくれると思います。
🗳️ あなたの職場ではどうですか?
このシリーズを見る
→ チームワーク進化論(全5回):Microsoft 365×Teamsで変わる共同作業
🧭仕事の「やり方」を変える前に、一度「状況」を整理しませんか? ツールを整えても拭えない違和感があるなら、それは職場文化の土壌を整えるタイミングかもしれません。今の歩みを重くしている「正体」を言葉にし、次の一歩を導き出す対話セッション Compass をご案内しています。
