DXのステージ、説明できますか? ― 職場で“納得して進む”ための共通フレームワーク
Microsoft 365 を導入したものの、現場の働き方が大きく変わった実感がない。
PowerApps を作っても、特定のチームでしか使われない。
生成AIの活用も話題には上がるが、「それって自分たちには関係あるの?」と受け止められてしまう。
こうした課題の背景には、「今、私たちはどの段階にいるのか」という共通理解の欠如があります。
DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が広がる中で、
その“進み方の順番”が現場で共有されていないことが、
導入が定着しない一因となっているのです。
DXには、段階的なステップが存在します
DXは一足飛びで成果が出るものではなく、段階的に成熟していくプロセスです。
このデジタル化の考え方は、もともとヨーロッパで2000年代初頭から提唱されたDXの基本概念に基づいており、サワモト式ではそれを現場で使いやすい形に再構成し、Microsoft 365のツールに当てはめて解説しています。
もちろん、それぞれのステージでツールを導入すれば、局所的には効果が出ます。
Teams を導入すれば情報共有はスムーズになり、PowerAutomate を使えば申請業務が自動化されます。
ただし、本来DXに臨んでいる効果――
つまり「デジタル時代の組織の変革」や「データ活用による業務の進化」にたどり着くには、
段階を踏み、ツール同士をつなげて“データを活用する流れ”を計画する必要があります。
具体的には、
- ステージ1で データをデジタル上に蓄積し、
- ステージ2で 業務全体に統合・連携させ、
- ステージ3で 蓄積されたデータを分析・活用して変革へつなげる
という一連の流れを描く必要があります。
DXを「単なるツールの導入」ではなく、「データを軸にした進化のプロセス」として捉えることが求められています。
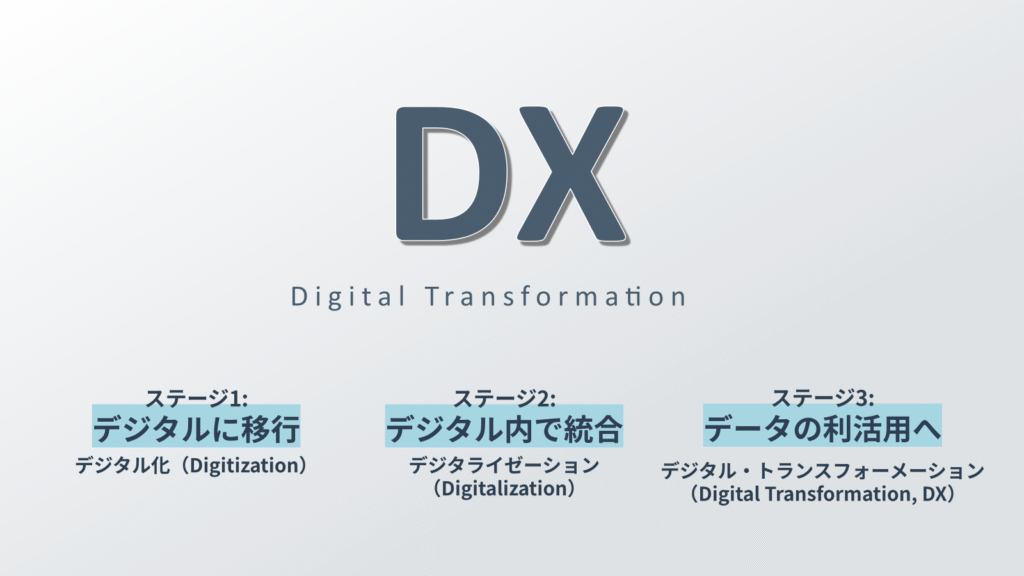
サワモト式が定義する「DXの3ステージ」
ステージ1:Digitization(デジタル化)
紙の資料や口頭のやりとりを、デジタルに置き換える段階。ただ、まだコピペや紙の利用も多く、仕事のやり方は変わっていません。
例:Teams の導入、ファイル共有のクラウド化など
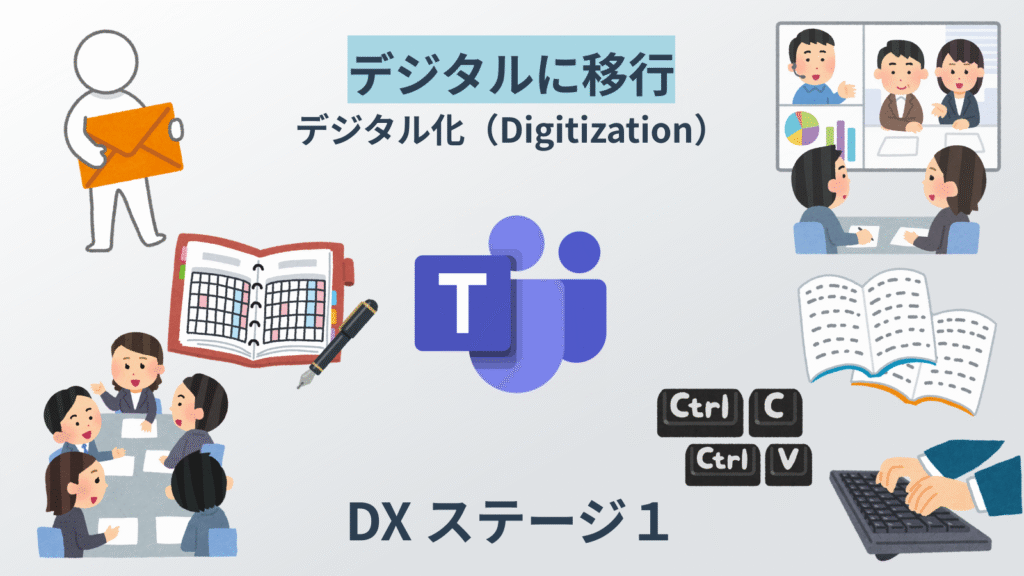
ステージ2:Digitalization(業務の統合)
バラバラだった業務や情報を、デジタル上で統合していく段階。データがアプリ間で受け渡しされ、情報に流れが生まれます。
例:PowerApps による申請業務、Power Automate による処理の自動化
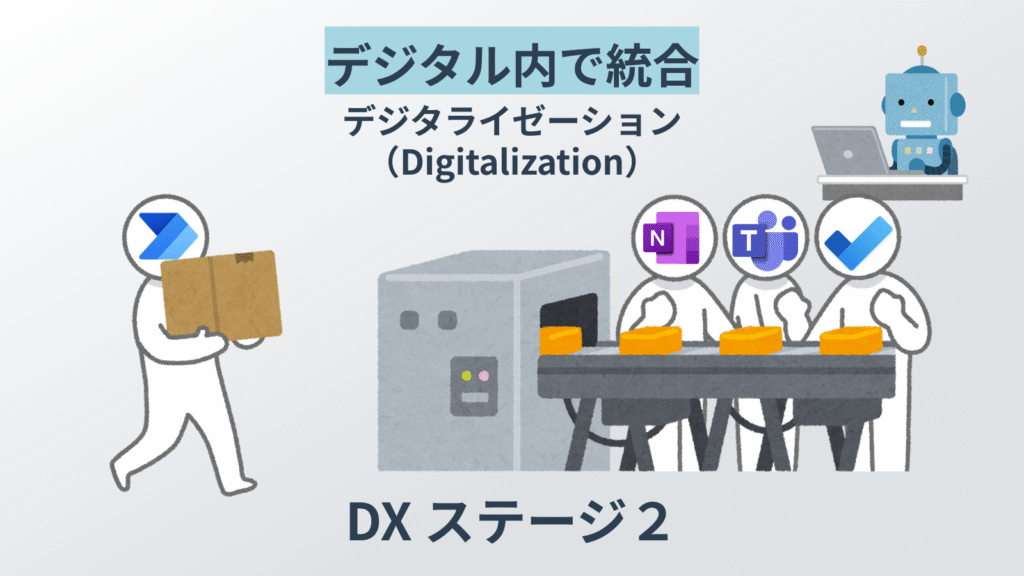
ステージ3:Digital Transformation(変革と活用)
蓄積されたデータを活用し、意思決定や業務そのものが変わっていく段階。アプリの活用により、業務で集まった働き方のデータから、「学び」と「気づき」を受け、働き方の分析、現場でのリアルタイムな意思決定が可能になります。
例:Power BI によるデータ分析、Copilot や生成AIの業務活用
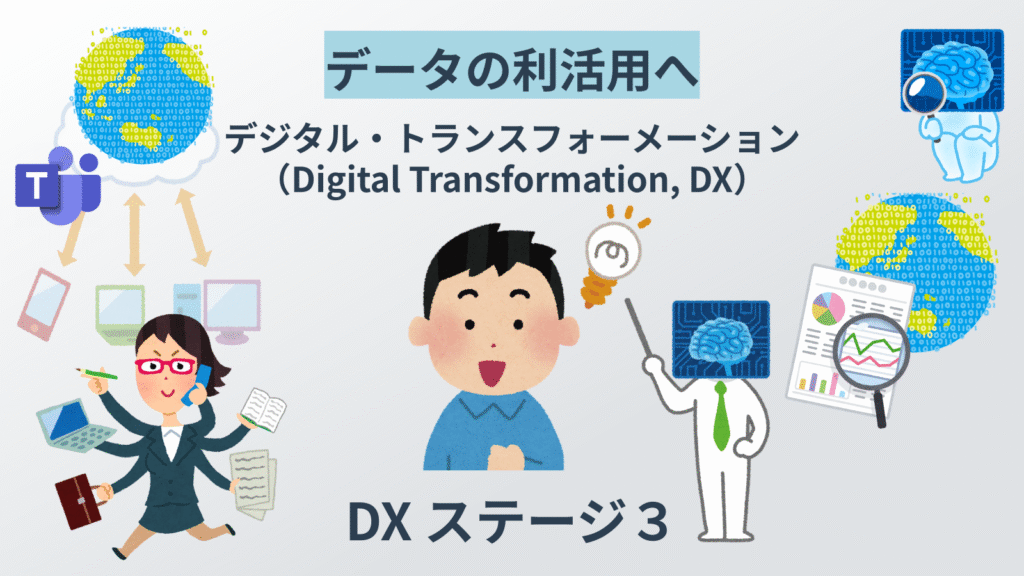
「いま、私たちはどこにいるのか?」を共有することの意味
この3ステージのフレームワークを導入することで、
「自分たちは今、ステージ1なのか、それとも2なのか?」と
職場ごとの現在地を共有し、次の一手を議論できる土台が生まれます。
DXが進まない理由の多くは、現場のメンバーが
「なぜ今このツールを導入するのか」を理解しきれていないことにあります。
ツール単位での導入や研修では、全体像が見えず、
「なんとなく始まったけれど、結局使われなくなった」といった状態に陥りがちです。
DXは「専門家のもの」から「職場全体の会話」へ
従来のOffice製品は、ユーザーが個別にアプリを起動し、ファイルを作成・保存するためのものでした。業務の一部を支援するツールではありましたが、あくまで“パソコンの中”で完結するものが中心でした。
しかし現在の Microsoft 365 をはじめとするクラウドベースのツール群は、
単なる「ファイル作成ソフト」ではありません。
Teams や Power Platform、Copilotなどは、
職場で行われている会話や業務プロセスの“すき間”に自然と入り込み、業務そのものの一部として機能するようになっています。
その結果、こうしたツールの活用は「個人のITスキル」だけでは完結しなくなりました。
“職場全体の働き方や情報の流れ”としてどう使うかを、チームで話し合う必要が出てきているのです。
この「DXの3ステージ」を職場全体で共有することで、
現場の理解が深まり、「納得して取り組む」状態が生まれます。
サワモト式が目指すのは、職場で話せる“共通の地図”
サワモト式では、この3ステージをシンプルに示した図解と、
「自分たちの職場の位置」を見える化できる診断ツールを提供しています。
目的は、「理解」ではなく「共有」にあります。
「今の私たちはステージ1。まずはここを固めてから次に進もう」
「ステージ3を目指したいけれど、まだ2の整備が不十分かもしれない」
そんな会話が自然に生まれる状態こそが、DXが現場に根付く第一歩です。
まとめ:あなたの職場は、いまどのステージにいますか?
DXを進めるには、戦略やツールだけでなく、
現場が「自分ごととして話せる状態」をつくることが不可欠です。
そのためには、抽象的なビジョンではなく、
自分たちの足元を確認できる“地図”が必要です。
DXの3ステージは、その最初の一歩を支えるフレームワークとして機能します。
🧭仕事の「やり方」を変える前に、一度「状況」を整理しませんか? ツールを整えても拭えない違和感があるなら、それは職場文化の土壌を整えるタイミングかもしれません。今の歩みを重くしている「正体」を言葉にし、次の一歩を導き出す対話セッション Compass をご案内しています。
